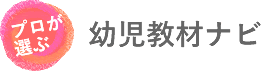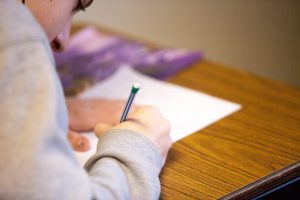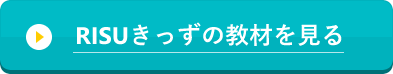もうすぐ入学のシーズンですね。春から小学生になる子どもを持つ親御さんにとっては、ランドセルや文房具などを揃えるのに忙しいことでしょう。
そして、必要なものを揃えるのと同じくらい大事なのが、家庭内での学習準備です。あらかじめ基本を身につけておくことで、新学期からスムーズに学校の勉強についていけるようになります。
先取りしすぎると授業がつまらなくなるという話もありますが、それでも最低限おさえておいた方がよいことというのはあります。
今回は、小学校へ入学する前の学習準備として大切なことを、いくつか解説していきます。
1.あいさつができる
あいさつができることは小学生だけでなく、大人も含めた全員にとってコミュニケーションの第一歩となります。
以下の4つは最低限、意識せずに言えるようにしたいです。
- おはようございます
- こんにちは
- さようなら
- ありがとうございます
また、あいさつに限らず、「はい」や「いいえ」などの返事も大変重要です。授業で何がわかって、何がわからないのかが先生に伝わらないことにはフォローを期待できません。
近所の人や家庭内であいさつの練習をしておくといいでしょう。
2.人の話を聞ける
小学校での授業は、基本的に1時限が45分となっています。休憩時間は5分から10分です。
実は大人でも集中力が持続するのは15分という研究があります。5分間隔で45分の授業を集中して受講するのは、大人でも難しいことなのです。まして、好奇心が旺盛でいろいろなものに興味が移る子どものことですから、授業を最初から最後まで集中して受け続けるのは、かなり厳しいと思われます。
それは先生も認知していることなので、生徒の注意を引けるよう、様々な工夫を凝らしています。先生が呼びかけたり強調したりしたポイントで、話を理解して飲み込めるかどうかは児童によって差が出ます。
授業全体を通してではなく、要所要所でスイッチを入れて、先生の話を聞けるようになれれば、学習の効率も上がります。そのためにも、集中して人の話を聞く力を訓練することが重要になります。
その力があれば、たとえ話を聞いてもわからなかった時でも、わからないということがわかります。自分の苦手とする部分がわかるというのは、予習や復習の際にもかかわる大事なことです。
絵本の読み聞かせ
読み聞かせは、人の話を聞く習慣・力を身につけされるのに最適な手段です。
ものがたりに興味がないお子さんの場合には、なぞなぞやクイズでもいいでしょう。お子さんのそれぞれの興味に合わせて、親御さんがお話しをしてあげればよいと思います。
3.ひらがなの読み書きができる
ひらがなとカタカナの読み書きは、小学校入学の時点である程度できているものとして扱われます。
あるアンケートによれば、年長の1月の時点で、読み書きのできる子は40%を超えています。つまり、小学校入学時の子どもの約半分は読み書きができるのです。
まわりの子から遅れないためにも、50音の読み書きはできるようにしておく方が無難です。
最低限でも、自分の名前ぐらいは読み書きできるようにしておくといいでしょう。テストやプリントなどの提出物や、教科書やノートなどの持ち物には名前を書く必要があります。
練習はまずは読みから、続いて書きの順番で進めるのがよいと思います。
読みの練習としては、先ほども挙げた絵本の読み聞かせの時に、お子さんにも一緒に音読させるのがおすすめです。
4.数をかぞえられる
1から10、できれば1から20ぐらいまでが理解できていればいいでしょう。
小学生の苦手な教科・嫌いな教科の1位は算数です。その一方で、好きな教科1位でもあります。つまり、算数は得意な子と苦手な子の差が大きい教科なのです。
当たり前のことですが、授業では学年を重ねるにつれ、前年に習ったことを前提として新しいことを教えられます。漢字や社会などは違い、毎年の内容がつながっているので、前年の内容がわかっていなければ、次の年の内容もまったくわからなくなってしまいます。
スタート地点でつまずかずに足し算の勉強ができるよう、数え方を入学前に予習しておくことをおすすめします。
関連記事はこちら⇒幼児から算数が好きになる!家庭でできる教材比較
指を使う
数字をかぞえる方法には、おはじきや身のまわりのものを使ったりするものもありますが、まずは一番手軽な、指を使って計算することを覚えましょう。
指はどこでも持ち運び可能な電卓のようなものです。高学年になっても指を使っていては不安かもしれませんが、はじめは指を使って覚えるのがわかりやすくていいでしょう。
紙に書いて覚えさせる
数字もひらがなやカタカナと同じで、文字を覚えなければいけません。ひらがなの練習と同様に、書かせる練習も不可欠でしょう。
タブレット教材を使う
最近ではタブレット教材の中にも、幼児向けのものが登場しています。カラフルなイラストやアニメーションで、小さな子どもにわかりやすく勉強を教えてくれます。
特におすすめなのがRISUきっずです。
算数に特化したタブレット教材となっていて、数を覚えるのに最適です。入学準備の段階で英語も国語も算数も全教科を勉強させるのは大変なので、まずは数を数えるところから始めて算数に集中するのがいいでしょう。
しかもRISUきっずには、問題文の音声読み上げサポート機能があります。読み書きの学習がまだのお子さんでも取り組めますし、これ自体がひらがなの学習にもつながります。
関連記事はこちら⇒タブレットを使った幼児教育ってどうなの?気になる効果やオススメ製品は?
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら
5.学習習慣をつくる
授業もそうですが、家庭内の学習時間も小学生になると格段に伸びてきます。
学校では宿題を出されますし、内容を理解するためにも自発的な予習・復習が必要です。
ひらがなを覚えたり、数を数えたりしながら、入学以後に活きてくる学習習慣を形成する必要があります。幼い時に身につけておいた学習習慣は、小学校に限らず、中学高校大学でも大きな財産になります。
最初は10分からでも構わないでしょう。ドリルでもプリントでもタブレットでも、毎日継続的に続ける習慣が生まれるのであれば、どれも有効といえます。RISUきっずの場合も、一回の所要時間は10分ほどのようです。
6.時計がわかる
授業は45分、休み時間は何分、給食の時間は何分など、学校では時間割に沿って動く必要があります。
チャイムで誘導されるとはいうものの、基本的には子どもが自分自身で時間の管理をしなくてはなりません。
年長のうちは、正確な時間は読み取れなくても、時計を読む習慣をつけるといいでしょう。具体的には、「針がどの位置まで来たら勉強終わり」などのルールを共有するのがおすすめです。この方法を使えば、学習が習慣化されるだけでなく、文字盤を見て数の勉強にもなります。
RISUきっずでも時計のレッスンは用意されています。また、RISUきっずに限らずとも、時計の理解力を問い、鍛える問題の豊富なタブレット教材は多いようです。
7.まとめ
春からの入学準備として必要なことは大きくわけると、
- 学習の基礎事項を知っておく(数字やひらがなを理解できる)
- 学習の習慣をつけておく(時計を見て行動ができる)
- 集団行動をとれるようにする(あいさつ、人の話を聞く)
の3点になります。
その対策として、読み聞かせやタブレット教材などをおすすめしました。
年長の子どもを持つ親御さんは、焦ることなく入学準備を進めてみてください。