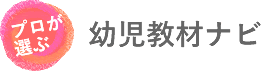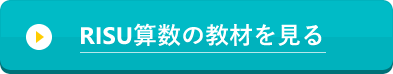現代では、小学生のふたりにひとりは習い事に通っているというデータがあります。また、4人にひとりは、ふたつ以上の習い事に通っているとも言われており、多忙を極めている家庭も少なくはないようです。
多くの子どもが習い事に励む一方で、勉強もおろそかにしてほしくないと考える親御さんもいるでしょう。習い事のせいで、学校の勉強についていけなくなったり、受験をあきらめたりするのは、なんとしても避けたいところです。
そのため、限られた放課後の時間を有効活用するために、子どもの個性やご家庭のライフスタイルなどにあわせて、適切な習い事を選択する必要があります。
今回は、習い事の種類ごとのメリットを確認し、なおかつ習い事と並行して短い時間でできる効果的な勉強法についても考えていきます。
習い事選びや勉強の仕方の参考にしてみてくださいね。
親が子どもに通わせたい人気の習い事
習い事といっても、さまざまなものがあります。ここでは親御さんにも人気の習い事について、メリットを考えていきます。
スイミング
スポーツの習い事全般に共通して言えることですが、まず第一に体力や免疫力が鍛えられます。それによって怪我をしにくく、病気になりにくい子どもに成長することが期待されます。
スイミングの場合は泳ぎの習得そのものも大事です。水泳を早めに習得しておけば、学校の水泳授業や、休みに海やプールへ行く時に簡単に泳ぐことができ、おおいに役立つでしょう。また、高められた心肺能力は、持久力を試される陸上などの他のスポーツにも活用できます。
ピアノ、音楽教室
今では、男女関係なく通う子が多いとされるピアノ教室や音楽教室では、音感やリズム感を学べるので、学校での音楽の授業で活きてくるでしょう。
リコーダーや歌の授業の際にメモや暗記に頼ることなく、楽譜がすんなりと読めると、お子さんの負担はとても減ります。譜面上のさまざまな情報を理解して表現できるようになると、表現力が育てられるでしょう。
体操
体育の基本となる、バランス感覚や身体の柔軟性が身につきます。
運動習慣がまだの幼児には、正しい姿勢が身につき、身体の形成にもいい影響を与えますし、はじめは簡単なマット運動から始めるので、体育を苦手と感じている低学年の小学生にも親しみやすく、とてもおすすめです。基礎体力や基本的な運動神経を手にいれることで、ほかのスポーツへの応用がききます。
サッカーや野球など
サッカーや野球がスイミングや体操と大きく違うのは、チームで競うスポーツであるということです。そのため、チームメートと一緒に力をあわせて練習に励んでいるうちに、おのずと協調性が身につきます。
親としても、子どもと一緒に遊んだり、観戦を楽しんだりしやすいジャンルです。
柔道や空手など
他のスポーツと異なり、礼儀やマナーを身につけてほしいという親御さんが通わせていることが多い習い事のひとつです。
試合前後の礼や稽古でのあいさつを指導されるなど、礼儀を重んじるスポーツでもあるので、勝敗や年齢にかかわらず相手を尊重する人間性の成長を期待できるのが、武道のよいところではないでしょうか。
将棋
頭を使った勉強になる習い事として人気です。
将棋のゴールは相手の王様を取ること。そのゴールに向かっては、いろいろな手が可能です。相手や局面にあわせて、自分の次の一手を決める。これは柔軟な論理的思考力を鍛えてくれるでしょう。算数や数学の問題を解く力にもつながります。
武道と同様、試合前後の礼は欠かせません。年長者と接する機会も多いので、自然と礼儀が身につくのも魅力です。
プログラミング
IT化の時代にあわせて、今最も人気になっている習い事です。どうせだったら、将来役に立ちそうな習い事をさせたいという親たちに人気のようです。
また、2020年からは学校の必修科目にもなる予定です。今はまだ学校では必修でないからこそ、今のうちに習い事として学んでおくことで差をつけられるでしょう。
関連記事はこちら⇒習い事人気ランキング1位はプログラミング!どこに通わせたらいい?
習い事のデメリット
ここまでいくつか習い事をざっくり紹介していきましたが、残念ながらメリットだけではないのが現実です。
時間がとられる
放課後の時間は限りあるものです。
その時間を習い事に費やすと、友達と自由に遊んだり、宿題をしたり、勉強の予習復習をする時間が必然的に減ってしまいます。複数の習い事をしているお子さんは、よりその傾向が強いでしょう。
あるアンケートのよると、心や身体の疲れについてたずねたところ、「忙しい」と感じている子どもは、小学生で51.2%と半数を超えていることがわかりました。
その原因のひとつとして、少子化による子どもひとりあたりへの習い事の投資量が挙げられているのです。
親の手間がかかる
子どもがまだ小さかったり、通う場所が遠かったりする場合は、送り迎えの必要が生じてしまうなど、習い事には親の手間がかかってしまうことが多いです。
また、ピアノのように、高価な道具を用意しなければならないこともあります。
家での練習に親がつきあわないといけないことも多いです。忙しい親御さんにとっては、たいへんな負担となるでしょう。
習い事と両立できる勉強法
習い事は手間暇がかかるといっても、やはりメリットを考えるとやらせてあげたいですよね。すでに習い事をしている場合についても、やはり続けさせてあげたいものです。
けれども、勉強の時間が必要なのも確かです。
小学生も低学年のうちは5時間授業と比較的はやく帰ってこれるので、放課後は習い事以外にも時間はとりやすいです。しかし、中学年高学年になってくると、6時間授業になり、下校時間も遅くなります。学年が進むにつれて、学習内容はよりむずかしくなり、宿題以外の自学自習が必要とされてきます。
習い事もさせたいし、勉強もさせたい
今回は、少ないスキマ時間でも効果的に学習できる方法として、タブレット教材をおすすめします。タブレット教材は、習い事と並行して活用するのにとても便利です。
タブレット教材のメリット
通う手間がない
通信教育全般にもいえることですが、タブレット教材の場合、学校や塾、習い事のように、移動時間がとられることはありません。思い立った時にすぐ始めることが可能です。はじめからおわりまで、すべて家の中で完結しているので、送り迎えの苦労もありません。
親の負担が減る
タブレット教材は添削、解説、復習などをすべて機械がしてくれるので、親の手間はかかりません。丸つけの時間が減ることで、親の時短にも繋がります。教科書より動きがあるので、子どもが自発的に興味を持ちやすいし、付録もついてこないので、付録に夢中で勉強そっちのけ、なんてこともありません。
外に持ち運べる
タブレットという性質上、インターネット接続が必要になってきますが、ドリルなどと違い、筆記用具などあれもこれもを持ち運ぶ必要はありません。習い事の施設で無料Wi-Fiが解放されていれば、待ち時間に進めることだってできます。ポケットWi-Fiや車載Wi-Fiを用意しておけば、送り迎えの時間も活用できます。帰省中の学習も簡単です。
ひとりひとりに合っている
ひとりひとりのデータから、その子に最適化した問題を解くことができます。すべてのお子さんが自分のペースで勉強を進めることができるので、習い事に忙しくて学校の勉強に遅れてしまった子が遅れを取り戻したり、これから忙しくなるのを見越して先に勉強しておいたりすることができます。
関連記事はこちら⇒タブレット学習のメリット・デメリットとは?
RISU算数
タブレット教材の中でもおすすめのひとつが、RISU算数です。
以前通っていた塾は、子供のやる気が続かなかったため退会しました。RISUに関してはゲーム感覚で楽しめるということもあり、自ら進んで学習し、旅先にも忘れず持参してやるほど今では熱中しています。
といった親御さんの声もあるとおり、さきほど説明したタブレット教材の利点を、RISU算数はきちんとカバーしています。
算数の学習に特化したタブレット製品なのですが、算数に必要な計算力はもちろん、思考力や空間把握能力など、他分野への応用が可能な柔軟なスキルも高めることができる教材です。
教材中にふくまれる文章題の文量は、国語の教科書と変わらないので、それを読んで問題を考えることで、読解力も鍛えられます。
特筆すべきは、1日の所要時間です。平均学習時間は15分未満なので、忙しい生活のなかでも、間をぬって続けることが可能です。
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら
まとめ
子どものためを思ってはじめた習い事が、親の負担になるだけでなく、子どもにとっても勉強時間が足りなくなってしまうことがあります。
いろいろな習い事に通わせているご家庭こそ、そのようになってしまいがちです.
大好きな習い事を続けさせたいけど、勉強もしっかりとしてほしい。
そんな思いにうまくこたえられるのが、タブレット教材ではないでしょうか。