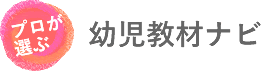お勉強といえば従来、鉛筆で紙に書くものでした。
しかし最近では、タブレットなどを用いてゲーム形式で勉強できる教材が人気>strong>を集めています。
しかしゲームで勉強をさせることには、親世代は抵抗があります。
本記事では「幼児期には何を目標に勉強すべきか」、「目標を踏まえ、幼児期にゲームを用いて勉強することのメリットとデメリット」
についてご紹介します。
そもそも幼児教育では何を目標にするべきなの?
小学校の入学後の勉強については、成績がどれだけ上がるかが重視すべきポイントになります。
しかし、幼児教育に関しては、小学校の教育とは事情が違います。
成績の伸びよりも重視すべきポイントが3つあります。
1.自宅での学習習慣をつくり、小学校入学に備える

小学校入学後に順調なスタートを切るために、お家でお勉強する習慣は欠かせません。
小学校に入学した後、躓いてしまうお子さんが多くいます。
毎日の宿題をこなすのが大変で、勉強自体が嫌になってしまい、つまずくようになるのです。
学校では授業で習ったことを定着させるために宿題を出しており、それを前提にして授業カリキュラムが進んでいきます。
したがって、毎日出される宿題をこなせないと、授業についていくのが難しくなってしまいます。
しかし入学前に家庭学習の習慣がなかったお子さんにとって、毎日机に向かうのは至難の業です。
宿題をこなすのに苦戦するうち、いつのまにか授業についていけなくなってしまうのです。
小学校に入学したからと言ってすぐに習慣は身につくものではありません。
入学前に机に向かう習慣を作っておきましょう。
2.勉強=楽しいという感覚を持ってもらう

学習習慣の形成のためには、「勉強は楽しいのだ」という感覚を身につけることは欠かせません。
楽しいことには自分から毎日積極的に取り組んでくれるからです。
「勉強はつまらない、嫌い」という感覚を持たないように気を配ってあげることが必要です。
3.勉強への自信をはぐくむ

誰しも自信のないことに取り組むのは気が進まないものです。
「自分は勉強ができないかもしれない」と思ってしまうと、勉強するのが億劫になり、そのうちに苦手な分野ができてますます勉強に対する自信を失ってしまう、という悪循環にはまってしまいます。
小学校で本格的なお勉強が始まった後にこのような事態に陥らないためにも、就学前の教育では「自分は勉強ができるのだ」という自信をはぐくむことを目標にしましょう。
ゲームをつかった教育のメリット
「学習習慣を身に着ける」、「勉強は楽しいと思ってもらう」、「自信をはぐくむ」、という目標を念頭に置いた際、ゲームを用いた教育にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
1.「勉強=楽しい」と思ってもらいやすい

普段遊んでいるゲームと同じような感覚で勉強することができるので、勉強に対する抵抗を持つことなく取り組んでもらえ、「勉強は楽しいのだ」、という感覚を持ってもらいやすくなります。
そして子供は楽しいことには進んで取り組んでくれます。
毎日ゲーム感覚で勉強するうちに自然と自分から机に向かうことが習慣として定着するのです。
2.「書く」煩わしさがない

また、タブレットでは「書く」という煩わしさがありません。
未就学のお子さんのなかにはひらがななどの字を習いたてのお子さんも多く、すらすらと文字を書くことがまだできません。
したがって、たとえば算数などを勉強する際に鉛筆と紙を用いると、内容は理解できて面白いと感じるのに、「書く」という作業が煩わしいために勉強が嫌になってしまうお子さんも多くいます。
せっかく内容を分かっているのに、これで勉強を嫌だと感じるのはもったいないことです。
ゲーム教材を用いると、「書く」という作業に煩わされず内容そのものに集中できます。
余計なところで勉強嫌いになってしまう可能性を無くすことができるのです。
3.動画などを用いた直観的な理解がしやすい
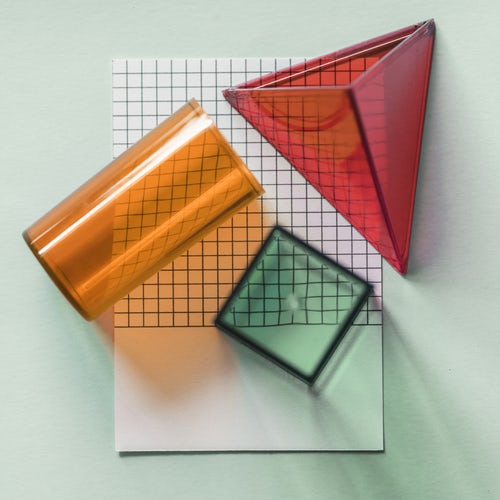
お家でドリルなどを用いて勉強する際は、説明の文章を読んだり、親御さんの説明を聞いたりしながらわからないところを理解していくことになります。
ところが、分野によっては口頭や文章の説明だけでは理解が難しいこともあります。
例えば算数の図形問題などがそうです。
立体や空間把握の分野では、言葉での説明よりも目で見てイメージを持つことが重要になります。
ゲームの中には鮮やかなグラフィックや動画を用いて解説をしてくれるものもあり、お子さんの理解をより促すことができます。
4.親御さんが忙しくても自分で勉強ができる
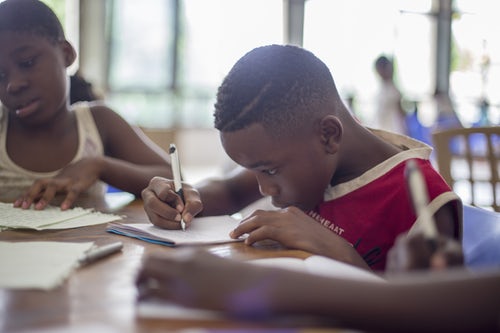
お家でドリルなどを用いて勉強する際、親御さんが付きっ切りで見てあげなくてはいけないことも少なくありません。
特にまるつけはお子さんがひとりでできない場合が多いため、親御さんがまる付けをしないと次の章に進めないといった事態がよく起こります。
ところが、毎日の家事やお仕事など親御さんは他にもこなさなくてはいけないことがたくさんあり、毎日時間を割いてお子さんの勉強を見ることは至難の業です。
親御さんが時間を取れるときだけ勉強をすることになってしまうと、結局毎日勉強する習慣の形成には至りません。
ゲーム形式の教材なら、まる付けもなどの些末な作業を機械が勝手に行ってくれるため、お子さんがいつでも一人で勉強をすることができます。
親御さんの予定や忙しさに左右されず、お子さんが毎日お勉強をすることができるのです。
ゲームをつかった教育のデメリット
一方で、ゲームを用いて勉強をする際にはこのようなデメリットもあります。
1.進む量にきまりがなく、任意である

たとえば塾などに通う場合、毎日・毎月やる分量が決められています。
一方、ゲームに関しては、分量について強制力がなくその子が進みたいときに進みたい分だけ進む形になります。
したがって、ゲーム形式の教材を用いると、毎日机に向かう習慣は付きますが、与えられた量をすべてこなすことには慣れることができません。
2.長時間つかわせることができない

ゲームの画面を見続けると、視力の低下が懸念されます。
短時間使う分には問題ありませんが、1時間、2時間単位の使用をすることはむずかしくなってきます。
したがって、長時間集中して問題に取り組む姿勢までは養ってあげることができません。
3.自分の成長を実感しづらい

自分がお勉強を頑張った結果、きちんと成績が伸びたことを実感できるとやる気が出ます。
「これだけ頑張ったんだ、自分はできるんだ」という自信にもつながります。
塾などのお教室に通う場合はテストがあり、全体の中での自分の立ち位置や、自分の成績の伸びについて実感するきっかけになります。
しかし、自分でゲームを使って勉強をすると、毎日漫然と問題を解くことになってしまい、成長を実感できる局面はありません。
どれだけ進歩しているのかわからないため特に達成感や自信を身に着けることなく終わってしまうことになってしまいます。
4.苦手を放置してしまいがち

ゲーム教材の場合、ものによっては解きたい分野を自分で選ぶことができます。
そこで、自分が好きな分野や得意な分野だけを解いてしまうお子さんもいます。
これでは苦手な問題を放っておいてしまうことになり、わからないところが克服できません。
まとめ
幼児期の教育では、大事にするべきことが小学校入学以降と異なります。
成績を伸ばすことそのものよりも、入学後の勉強にしっかりついていけるように学習習慣の形成や自信を養うことが大切になるのです。
そのような教育の実現のために、ゲームを用いた教育を行うことにはメリットがあります。
字の書けないお子さんでも無理なくゲーム感覚で楽しく取り組めます。
また親御さんの予定に左右されず勉強することができるため、毎日机に向かう習慣を養うことにつながります。
しかし、デメリットもあります。
机に向かった後、長時間集中したり、与えられた量の課題をこなし切る力を身に着けることは難しいほか、達成感や自信を身に着けることが難しいのです。
今回ご紹介したメリットデメリットを比較し、ゲームを用いた教材が本当にお子さんに合っているかを考え、導入するかどうか決めていきましょう。