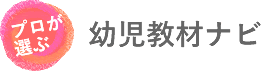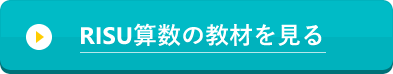学習指導要領の改訂によって、2020年からは小学校においてプログラミングが必修であつかわれることに決定しました。
プログラミングは英語の場合と異なり、単なる前倒しではなく、完全に新規の教科となるので、教育界にもかなりの動揺が走りました。
小学生や入学前の幼稚園生を子に持つ親御さんの中にも、プログラミングの必修化がどういうことか、よくわからないことが多いと思います。
親世代がそのような授業を受けていない以上、イメージがつかないのは無理もありません。
今回は、この必修化にはどういう背景、目的があるのか、授業準備として必要な心構えを解説していきます。
1.なぜプログラミングが必修化するのか

1.本格的なデジタル社会の到来
情報技術の発展で、自動化や遠隔化が急速に進んでいます。
ありとあらゆるものがコンピュータで制御されるように変わってきました。
人工知能の発達で、消える職業も多いと言われています。
現在でも、少なくとも90%の職業が基礎的なITスキルは最低限必要としている、という研究があります。
確かにパソコンを使わない職場はほとんどなくなったのではないでしょうか?
つまり、これからの時代を生き抜くためには、コンピュータの知識が必要なのです。
2.IT系人材の不足
さらに、日本ではコンピュータの専門職が足りていないのが現状です。
2020年までには37万人のIT人材が不足することがわかっています。
プログラミング教育を通してITリテラシーを広めると同時に、エンジニア自体の増加も目指されています。
2.プログラミング教育の目的

プログラミングよりむしろPC関連の情報機器との上手な付き合い方や、インターネットの危険性や倫理観を教えることが先なのでは。
技術だけでは豊かな生活には役立たないと思う。
プログラミング教育に反対する意見として、上のような声が散見されました。
多くの人は、プログラミングそのものを教えることがプログラミング教育の主目的だと勘違いされていますが、実際はそうではありません。
新しい学習指導要領では、プログラミング学習を次のように定義しています。
・ 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動。
・ 児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。
簡単にまとめると、パソコンやネットの基本的な使い方と、思考力をほどこすために、プログラミング教育が行われるのです。
つまり、プログラミングそのものの習得を目的にはしていないのです。
むしろ、懸念の声にあったようなパソコンとの上手な付き合い方や、ほかの教科にも活きる思考力を教えることを目的にしています。
IT技術者のなかでも次のような発言があるとおり、論理的思考力の向上にかんしては、特に期待されているようです。
プログラミングを学ぶということは、論理的思考力を学ぶということにつながります。
他にも、数学的センスや効率化、発想力、応用力などがあります。
それはきっと他の教科の勉強にも役立つのではないかと思います。実際の教育現場でも、プログラミング言語を書かせる予定はないようです。
あくまでプログラミングの仕組みを学びながら、論理的思考力を身につけるにすぎないようです。
もちろん必修化の背景にあるように、教育を受けた児童のなかから実際にエンジニアを目指す生徒が出てくるのも期待されています。
3.準備していおくといいこと
このようなプログラミング教育に向けて、今から家庭で準備できることもたくさんあります。
子どもがプログラミング教育についていけるか不安な方は、特に参考にされるといいでしょう。
1.すなおな心構えでいる

プログラミングを未知の世界のものだと、食わず嫌いしないで、すなおに受け入れる心持ちが必要です。
特にこれは親御さんにいえることです。
今の子どもたちはデジタルネイティブと呼ばれる世代で、電子機器に抵抗がありませんが、その親の世代にとっては、電子機器は当たり前のものではありませんでした。
子どもは親の考えに影響を受けやすいものです。
お子さんと一緒に電子機器に触れてみたり、機械がどうやって動いているのか話題にあげたりして、子どものプログラミングの興味を引き出してみましょう。
電子機器に触れさせる際にはただゲームで遊ばせるのではなく、タブレット教材などを利用して、うまく学習につなげるのがおすすめです。
2.プログラミングソフトを使う

どのようにプログラミングの学習を進めるのか、どんな教材を使うのかに興味がある場合は、プログラミングソフトを使ってみるのもひとつの手です。
今までのところ、小学校で実際に使うことになる教材は発表されていませんが、どのソフトを選んでも練習が無駄になることはありません。
1.Scratch
おすすめはScratchです。
推奨年齢8~16歳の世界で最も有名な子ども向けプログラミングソフトです。
プログラミング言語を使うことなく、ビジュアルを頼りに学習することができるので、親にも特別な知識はいりません。
日本語対応もしていて無料で使用可能です。
パソコンだけでなくスマホやタブレットでも使えるので、どの家庭でもすぐに始めることができます。
幼児向けにはScratch Jrが提供されています。
2.プログラミング
プログラミンは文部科学省が公開している子供向けウェブサイトです。
パソコンさえあれば、サイト上で簡単なアニメやゲームをつくることができます。
Scratchと同じように、実際にプログラミングをすることなく、ビジュアルで簡単にできるように設計されています。
指導要領を決める文部科学省によるサイトなので、実際に教育現場で使われることになる教材に1番近いものだと予想できます。
学校でどのように学習を進めるのかイメージする際には、最も最適な手段だといえます。
3.ブロックで遊ぶ

プログラミングとは、細かいパーツに分けられた命令を組み立てて、コンピュータに指令を出すことです。
だからこそ、論理的思考力が身につくといわれているのです。
つまり、子どもはどのパーツとどのパーツとを組み合わせたらプログラムが意図のとおちに動くか、よく考えなければならないのです。
この考えて組み立てる力は、ブロック遊びでも培われるものです。
実際にレゴが好きだった子で、プログラミングがすぐに得意になった子もいます。
家にブロックのおもちゃがあれば、これまで以上にそれらで遊ばせてみるのをおすすめします。
4.プログラミング教室に行ってみる

先生から受けるプログラミング教育のイメージをつかみたい場合は、開講中のプログラミング教室に実際に足を運んでみてもいいかもしれません。
体験教室を開催しているところが多いので、まずは体験から始めるといいでしょう。
気にいれば入塾するのもありです。
学校での必修授業が始まる前に先取りできていたら、子どもの負担も減るでしょう。
筆者のおすすめはRISU式ロボット・プログラミング教室です。
東京にある2教室では、見学や体験レッスンも随時受け入れています。
また、ロボットを通じて学ぶことで、子どもの興味をひきやすいといえそうです。
関連記事はこちら⇒習い事人気ランキング1位はプログラミング!どこに通わせたらいい?
4.まとめ
現在、高校の選択科目であるプログラミングが、小学校の必修授業となるのに合わせて、各家庭での準備が必要になっています。
必ずしもプログラミング自体に触れる必要はありませんが、少なくとも心構えだけはしておくのがいいでしょう。