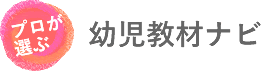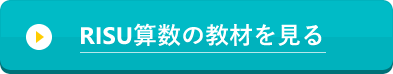受験勉強をするなら、学習塾に行くというのが主流になっています。
しかし、最近ではタブレット教材などのデジタル教材での学習が盛んです。
たとえば「チャレンジ」で知られる大手通信教育会社のベネッセでは、従来の紙教材に加えてタブレット教材での学習も取り入れており、今や大変人気のサービスとなっています。
もし学習塾だけでは不安な方は、タブレット教材を使った学習法を取り入れてみてもいでしょう。
今回は、タブレット教材のメリット・デメリットと、おすすめの学習法を紹介します。
タブレット教材のメリットとデメリット

まずは、タブレット教材のメリットとデメリットを紹介します。
それをもとに、今後タブレット教材を受験勉強に取り入れるかどうか、検討してみてください。
タブレット教材のメリット
効率よく学習できる
タブレット教材の強みは、学習効率が高まることです。
紙媒体の教材では「書く」という作業に時間が割かれるので、効率的に学習を進めるには、困難が生じることもあります。
しかしタブレットの場合は、自動的に間違えた問題が分かるように工夫されており、付箋を貼ったり、チェックを入れなくても簡単に復習に取り組めます。
隙間時間を有効に活用できる
受験勉強において成績アップの秘訣は、いかに隙間時間を有効に使っているかにかかっています。
たとえば通学中に単語帳を開いたり、学習塾のテキストを開いて復習をしたりしているかと思います。
ただ、テスト前などでは暗記物だけではなく、数学の見直しなどをしたくなるときもありますよね。
電車内などでいろんな科目の教科書やノートを取り出すのは流石に手間です。
しかし、タブレット教材ならそれだけで全科目の学習に取り組むことができるので、隙間時間を有効に活用することができます。
タブレット教材のデメリット
学習塾で使う紙教材に比べて記憶に残りにくい
タブレット教材は、間違えた問題が自動的に登録されていく機能がついてますので、余計な手間をかけずに復習するべき内容を把握できます。
一方、紙教材の場合は、間違えた問題をノートにまとめたり、チェックをいれたりする手間はかかります。
しかし、目で見るだけではなく手も動かしますので、記憶の定着度は紙媒体の方が高いです。
使い過ぎると身体に負担がかかる
タブレットが放つブルーライトは、目にいい影響は与えません。
そのため長時間の学習に向いている教材とは言えません。
また使用時間帯も限られます。
たとえば睡眠前にブルーライトを浴びると、睡眠の質が低下しますので寝る前にタブレット教材を使った学習は避けた方が良いですね。
タブレット教材を使ったおすすめ学習法3選

タブレット教材のメリット・デメリットを踏まえた上で、タブレット教材を使った学習法について紹介していきます。
これからタブレット教材を取り入れようと思っている人、もしくはすでに使っている人も参考にしていただけると嬉しいです。
状況によってタブレット教材と紙教材を使い分ける
タブレット教材のメリットと紙教材のメリットを組み合わせた勉強法を強くオススメいたします。
タブレット教材は隙間時間の有効活用に役立ち、紙教材は記憶の定着に役に立ちます。
そのため、休み時間や通学中のちょっとした時間はタブレット教材を使用し、じっくり復習したい部分をノートに手書きでまとめて記憶の定着を図る。
このような勉強法を取り入れると、タブレットの良さを活かしながら日々の学習に臨むことができます。
また、算数に特化したタブレット教材のRISU算数は「タブレットは定着しにくい」というデメリットを解消するための機能もあります。
「忘れてしまいがちなタイミングでの復習」と「間違いが多かった問題の復習」を組み合わせることで、むやみに全ての問題をやり直すこともなく、的確に地に足の着いた学習を進めることができます。
この機能により、本来なら定着しにくいタブレット教材で、紙教材並みの定着力を実現し、子どもの学力を確実に伸ばすことができます。
自分で答えを導くことを意識した学習に取り組む
タブレット教材は、面白いアニメーションや背景のデザインなど、勉強が楽しくなるようにいろんな工夫がされています。
そのため、学習を習慣付けるには最適な教材です。
しかし、内容を理解することばかりに夢中になって、自分で答えを足すことに意識が行かないこともあります。
分からない問題を自分で解決ができなければ、基本的な問題は十分に対応できても応用が利きません。
そのため、タブレット教材から学んだことを友達や親に教えたり、寝る前にその日に学んだことを手書きでまとめるといった工夫も必要です。
「なぜ?」を追求する
タブレット教材の問題点としてよくあげられているのが「答えをすぐに見ることができること」です。
なぜすぐに答えを見てしまうことがいけないのかというと、自分で考えられるところまで考えずに答えを見てしまうからです。
そのような勉強の仕方だと、考える力が育ちません。
つまり、「答えをすぐ見ること」が問題なのではなく、「考える力が伸びないこと」が問題なのです。
この問題は、答えを見た後に「なぜその答えになるのだろうか?」という疑問を追求し、その疑問を解消することで解決できます。
すぐに答えが見れることに甘えることなく、「なぜ?」を追求することが、タブレット教材の価値を最大限発揮するための秘訣です。
子どものやる気が持続するおすすめのタブレット教材
タブレット教材のデメリットを解消しながら、子どもが楽しみながら学ぶことのできるおすすめの教材はRISU算数です。
<RISU算数のおすすめポイント>
- 「鬼モード」や「こたえあわせミス」といった独自のコンテンツ機能で子どものやる気が持続する工夫がされている
- 子どもの「ちょうどいい」ところから学習を始められる
- アニメーション解説で飽きる楽しく学習に取り組める
- つまづきを感知して、子どもが楽しめるフォローアップ動画で学習をサポートする
- 家族全員でお得に楽しめる会員だけの優待制度(RISU Prime)も充実
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら
タブレット教材を使いこなそう
いかがでしょうか。
今回は、タブレット教材を使った学習法について紹介しました。
タブレット教材は、紙教材とは違った魅力を持った学習媒体です。
両者の良さを活かせるような学習ができれば、必ず今まで以上に受験勉強も効率的に進めることができるでしょう。