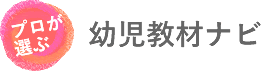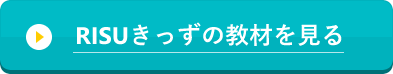幼児教育で名前を聞くことも多い七田式。
なかでもカリキュラムの中で用いられるフラッシュカードは珍しいと注目を集めています。
ところが最近、フラッシュカードに関する悪いうわさがあるようです。
そもそも七田式やフラッシュカードとはどんなものなのか、どんな弊害がうわさされているのか、原因は何か、予防できるのか、などの疑問にお答えしたいと思います。
1.七田式とは?
主に0歳から小学生のお子さんを対象にした教室です。
様々なコースの中で特に人気があるのが小学校未就学児むけの【幼児コース】です。
今回話題に上っているフラッシュカードは幼児コースのカリキュラムのうちの1つです。
他の幼児教室や塾と比較して、七田式には2つの特徴があります。
1.親御さんもレッスンに参加
他の教室であればお子さんがひとりでレッスンを受けます。
親御さんは送り迎えのみを担当するか、教室の遠いところで様子を見ているだけになります。
ところが七田式の場合は親御さんがレッスン中ずっとお子さんに付き添い、親御さんも一緒に指導を受けることになります。
なぜこのような形式なのでしょう。
それは、七田式が「全人格教育」を掲げているからです。
ただ単に学力を伸ばしてあげるだけでなく、心をはぐくむこと、健やかな体をはぐくもことを含め、その子が持っている元来の才能を開花させることを目指しています。
そのため教室で先生が教えてあげるだけでなく、お家で親御さんがお子さんにどのように接するかが大切になってくるのです。
2.右脳を育てる教育
左脳は論理脳・デジタル脳などと呼ばれます。
読むこと、書くこと、話すこと、文字の認識、数理的推理、論理的思考などを担当しています。
その一方で右脳はよくイメージ脳、感覚脳、芸術脳などと呼ばれます。
イメージの記憶、直観、ひらめきなどを司っており、全体的な情報処理を受け持っています。
学習塾などでは左脳に焦点が当たることが多い一方、七田式では後者の右脳にも焦点を当てて直観やひらめきなどをはぐくむ点に特徴があります。
2.フラッシュカードとは
フラッシュカードとは、絵や文字や数字などが描かれた沢山のカードです。
これらを短時間のうちの早いスピードで見せることで右脳を刺激し、感覚的に覚えさせようとするものになっています。
1枚1秒程度でどんどんめくってしまうため左脳はついていけず、視覚的に情報が脳に送り込まれることになるのです。
七田式の特徴である”右脳をはぐくむ”という文脈で取り入れられています。
【語彙力・理解力・表現力をつける】、【見たものをぱっと一瞬で記憶する】【左右の脳をつなぐ連結回路を育てる】ということが狙いのようです。
3.どんなうわさが流れているの?
上述のフラッシュカードについての悪いうわさをしばしば耳にします。
具体的には
- 突然、奇声を発するようになった
- 生気が見られず、元気がなくなった
- 子どもの自主性が育たない
- 子どもの思考力が育たない
などの声が聞かれます。
これらの弊害が起きるのはなぜでしょうか。
4.どうして弊害が起こるの?
七田式の弊害が起きるのはフラッシュカードのせいだけではないようです。
もちろん一因としてフラッシュカードの影響は懸念されていますが、他にも原因となり得るものがあります。
1.ほかのやるべきこと・やりたいことが抑圧されてしまう
これは七田式に限らず他の早期教育全般についてもあてはまることです。
1日24時間という限られた時間の中で幼児教育を実施するとなると、必然的に他のことに使える時間が少なくなります。
そこで遊ぶ時間や親子間でコミュニケーションをとる時間が減ってしまいます。
すると遊びから育まれる情緒的な発達が阻害される、親御さんからの愛情を子どもが十分感じられない、などの事態につながります。
また、子供に他にやりたいことがある場合、本当にやりたいことができずストレスを感じてしまうでしょう。
例えば運動や芸術を好む子・得意とする子に算数を無理やりやらせるとどうでしょう。
自分のやりたいことができないストレスや、得意な分野で才能を発揮できないつらさを感じてしまうことになります。
時間的制約により育むべきものが育めない、ストレスやつらさを感じてしまうということが、奇声や元気のなさの原因になり得ています。
2.じっくりと考えたい子には合わない
七田式では、1回50分という限られた時間の中に右脳を鍛えるカリキュラムと左脳を鍛えるカリキュラムを詰め込んでいます。
必然的に一つ一つのカリキュラムにさかれる時間は少なくなります。
また右脳を鍛えるセッションはとくに、じっくりと考えて答えを出すよりもひらめきで瞬時に答えを出すことが求められる内容となっています。
よってじっくりと考えて答えを出したい子にとってはせかされるようなプレッシャーを感じてしまいますし、最後まで自分の力で考え抜いたという達成感も感じにくい
のです。
自ら思考する姿勢が奪われてしまうのも、こなせすべきカリキュラムの多さや、瞬時に答えを求められる点に起因しています。
3.フラッシュカードと子どもの多動性には相関がある
フラッシュカードの使用時間と子供の多動傾向には相関があるというデータがあります。
このデータからうまれた、フラッシュカードの悪影響のについての仮説を2つ紹介します。
1つ目は、「フラッシュカードは子供の脳の発達に悪影響を与える」というものです。
子どもの脳は年齢を重ねるごとに発達していきます。
ある発達段階にいる子供に対して、「発達段階と合わない刺激をフラッシュカードによって送り込んでしまうと、脳の発達に支障をきたすのではないか」、ということだそうです。
この仮説に基づき進んでいる研究が実際にあるようです。
2つ目は、「フラッシュカードやドッツカードを大量に見させられるうちに子供の思考力や自主性が奪われてしまうのではないか」というものです。
注意したいのはフラッシュカードの悪影響を懸念する人は多いようですが、因果関係の有無は科学的に解明されていません。
5.予防できるの?
原因がきちんと解明されていないため、残念ながら完全に防ぐことは難しいでしょう。
しかしある程度までの予防はできます。
とくに原因としてご紹介したもののうち1点目、2点目に関しては
- 他のやりたいこと・やるべきことが抑圧されないように子供の様子をじっくりみる
- お家の勉強ではじっくり考えて達成感を得られるようにする
などの対策を講じることはできます。
しかし、肝心のフラッシュカードの悪影響について、詳細が分かっていない以上、悪影響の懸念を払拭することはできません。
6.まとめ
七田式は単に学力の向上を目指すだけではありません。
心や体を健やかにはぐくむこと、左脳だけでなく右脳も育ててあげることを目指しています。
取り入れられているカリキュラムの中には目新しいものもあり、注目をあつめています。
しかし、カリキュラムによる弊害のうわさは絶えません。
弊害はある程度予防できても、完全に防ぐことは難しいでしょう。
なぜなら、カリキュラムの1つであるフラッシュカードが脳に与える影響についてまだ完全に解明されていないからです。
幼児教育の方法は七田式以外にもたくさんあります。
お子さんの人生にとっていちばんよいものをえらんであげましょう。
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら