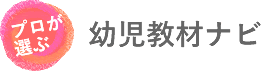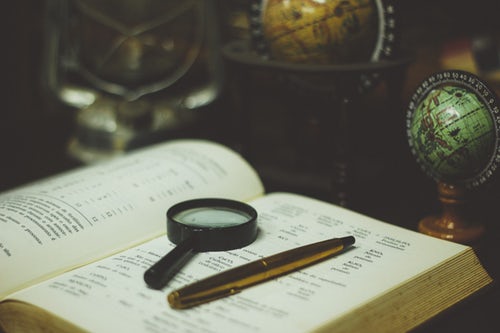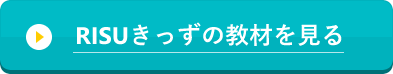名前を聞くことが増えた七田式ですが、賛否両論噂があるようです。
幼児教育のエキスパートとも言える七田式に、一体どんなデメリットがあるのでしょうか。
七田式の特徴と、入会して後悔してしまった方の体験談、さらにその原因についてまとめてみました。
1.七田式とは?
創業者の七田眞さんの名前から名付けられた教育カリキュラムです。
0歳から小学生まで幅広い年齢層のお子さんを対象にした教材ではありますが、その中でも特に、未就学のお子さん向けの幼児教育方法として人気があります。
七田式は学力の向上を目指すだけではありません。
お子さんの才能を開花させることを目標としています。
人気のある幼児コースの教室では一回あたりのレッスンは50分ほどで、お子さんだけでなく親御さんも一緒に受講をする点が特徴的です。
2.七田式の2つの教育方針
1.親御さんも子供に付き添い、指導を受ける
七田式の場合はカリキュラム中ずっと親御さんがお子さんに付き添ってあげます。
その中で親御さんもお子さんへの接し方について学んでいくことになります。
他の塾やお教室に通う場合と比較すると七田式はこの点でかなり特徴的です。
他の塾のほとんどではお子さんがひとりでレッスンを受けます。
親御さんは送り迎えのみをしてあげるか、付き添ってもすこし離れてお子さんを見守ることが多いです。
七田式ではなぜこのような形式をとっている理由は「全人格教育」を理念として掲げているからです。
学力向上のみならず、心をはぐくむことや、身体を健やかに育むことを目標として掲げています。
お教室で先生が教えることよりもむしろ、お家で親御さんがどのようにお子さんに接するかが大切なことになってくるのです。
2.右脳を育てる教育
人間の脳は左脳と右脳に分けられます。
左脳は論理脳・デジタル脳などと呼ばれます。
読むこと、書くこと、話すこと、文字の認識、数理的推理、論理的思考などをつかさどっています。
その一方で右脳はよくイメージ脳、感覚脳、芸術脳などと呼ばれます。
イメージの記憶、直観、ひらめきなどを司っており、全体的な情報処理を受け持っています。
他の学習塾などでは左脳のみに焦点が当たりがちでした。
一方で七田式では左脳だけでなく右脳にも焦点を当て、直観やひらめきなどをはぐくむことを重視する点に特徴があります。
3.カリキュラムの特徴
七田式の教室では、他の塾や幼児教室ではあまり見受けられないような独自の教育方法を取り入れています。
そのうち二つを紹介します。
1.フラッシュカード
フラッシュカードとは、絵や文字や数字などが描かれた沢山のカードです。
短時間のうちの早いスピードで見せることで右脳を刺激し、感覚的に覚えさせるために使用します。
1枚1秒程度でどんどんめくってしまうため左脳はついていけず、視覚的な情報が右脳に送り込まれることになります。
七田式においてこのカードを用いる狙いは、
・右脳の活性化
・語彙力・理解力・表現力
・見たものをぱっと一瞬で記憶する
・左右の脳をつなぐ連結回路を育てる
という点にあるようです。
2.ドッツカード
白地に赤丸が描かれたカードです。
フラッシュカードと同様にこれを短時間のうちに早いスピードで子供たちに見せてあげます。
すると、子どもが感覚的に数の概念を理解することができるようになります。
足し算や引き算、かけ算、わり算に役立つのはもちろんのこと、幾何や代数など複雑な数学の素地を育てることに主眼があります。
4.七田式の良いうわさ
七田式には悪いうわさだけではなく、もちろん良いうわさもあります。
七田式は才能を開花させることを目指してカリキュラムが組まれています。
理念の通り、卒業生の中には、自分の道で才能を開花させている子も多くいます。
たとえばフィギュアスケートで有名な本田姉妹もその卒業生です。
本田真凛さん、望結さん、紗来さんの三人は小学校入学前に七田式に通っていました。
周囲からは三人とも非常に想像力豊かだと評判です。
真凛さんはフィギュアスケートのふりを一度で皆覚えてしまうほどだそうです。
また、東大生の中には七田式をやっていた方が多いといううわさもあります。
実際、テレビ番組「さんまの東大方程式」でも七田式が紹介されています。
5.七田式に通って後悔したこと
七田式をはじめて後悔した、という声も残念ながらあります。
どんな後悔をしているのか、具体的に見ていきましょう。
1.突然奇声を発するようになった
小学校入学前に七田式に通っていたのですが、奇声を発したり、ずっと集中して机に向かえないようになってしまいました。(40代女性)
2歳の長女です。
幼児教室に通うようになると、夜な夜なギャー、ギャーと近所中に響きわたるような奇声を上げるようになった。
何ごとにもひどく攻撃的になった。
夜は、悲鳴のような大声で泣く。
近所の人は、子どもを虐待していると思って、たびたび警察に通報した。
警察が訪ねてくるようになった。
幼児教室を退会したら日に日に落ちついてきた。(30代女性)
2.生気が見られず、元気がなくなった
子どもが七田式を続けていました。
極度の怖がりです。
病的とまでは言いませんが、普通ではないです。(30歳女性)
大量のカードをフラッシュして見せることで右脳が活性化するという教育方針だった。
でも、3歳を迎える頃からうちの子どもはカベに向かって一人で独り言を言うようになった。
その独り言は、フラッシュカードで読み聞かせられた言葉ばかりです。
子どもは、何を見ても焦点が合わなくなった。
目に生気がなくなった。
全く笑わなくなった。(30代女性)
3.子どもの自主性が育たない
与えた課題はこなしてくれるが、いつも焦点の合わない目をしているし、自分から何かに働きかけなくなった。(30代女性)
4.子供の思考力が育たない
確かに記憶力はついたように思うが、粘り強く考えてくれない子になった。(30代女性)
6.七田式の弊害の原因
才能を伸ばせる子がいる一方で、なぜ七田式で後悔してしまう方がいるのでしょう。
考えうる原因を3つ紹介します。
1.やるべきこと・やりたいことが抑圧されてしまう
七田式に限らず他の早期教育全般にもあてはまることです。
幼児教育を実施するとなると、必然的に遊びなど他のことに使える時間が少なくなります。
そこで遊ぶ時間や親子間でのコミュニケーションをとる時間が減ると、遊びによる情緒的な発達が阻害される、親御さんからの愛情を子どもが十分感じられない、などの事態につながります。
また、子供に他にやりたいことがある場合、本当にやりたいことができずストレスを感じてしまうでしょう。
例えば運動や芸術を好む子に算数を無理やりやらせると、自分のやりたいことができないストレスや、得意な分野で才能を発揮できないつらさを感じてしまうことになります。
時間的制約によりはぐくむべきものがはぐくめない、ストレスやつらさを感じてしまうということが、奇声や元気のなさの原因と考えられます。
2.じっくりと考えたい子には合わない
七田式では、1回50分という限られた時間の中に右脳を鍛えるカリキュラムと左脳を鍛えるカリキュラムを詰め込んでいます。
必然的に一つ一つのカリキュラムにさかれる時間は少なくなります。
また、右脳を鍛えるセッションでは特にじっくりと考えて答えを出すよりもひらめきで瞬時に答えを出すことが求められる内容になっています。
じっくり考えたい子はせかされるようなプレッシャーを感じてしまいますし、自分の力で考え抜いたという達成感も感じにくいものになってしまいます。
自ら思考する姿勢が奪われてしまうのも、こなすべきカリキュラムの多さや、瞬時に答えを求められるという点などに起因しています。
3.フラッシュカードやドッツカードの悪影響
因果関係の有無まではまだ明らかになっていませんが、フラッシュカードやドッツカードは子供の脳の発育に悪影響があるという仮説の元進んでいる研究もアメリカにはあります。
またこれもあくまで仮説段階ではありますが、フラッシュカードやドッツカードを大量に見させられるうちに子供の思考力や自主性を奪ってしまうのではないかともいわれています。
7.まとめ
七田式は単なる学力の向上にとどまらず、その子の持つ可能性を開花させてあげることを目指す教材です。
卒業生の中には実際に様々な分野で活躍している子もいるようです。
一方で、お子さんが
・奇声を発するようになった
・生気がなくなった
・思考力が育たない
・自主性を失った
などの理由で後悔している方もいらっしゃるようです。
お子さんに合う教育方法かどうかを考えたうえで取り入れましょう。
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら