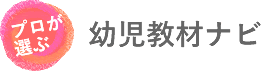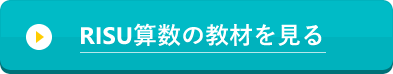最近はもう当たり前になったタブレット教材。中でも有名なのはスマイルゼミです。
塾と比較しても安価で、ゲームのような感覚で学べます。
お子さんにおねだりされてている親御さんもいらっしゃるでしょう。
「子どもがやりたいと言うなら始めてみようかな」、と思う一方で、「本当に続けてくれるのか」と心配な気持ちもあるでしょう。
「タブレット学習ってほんとうにつづくの?」、「続けるコツはあるの?」といった疑問にお答えします。
1.タブレット学習!どんな点で優れている?

1.ゲームのような感覚で

何とっても一番の特徴はそのハードルの低さにあります。
従来、勉強といえば紙と鉛筆でガリガリと問題を解くものでした。
一度慣れてしまえば平気になるお子さんもいらっしゃいますが、それでもなんとなく抵抗を感じるお子さんも多いはずです。
タブレットはゲームのような感覚で使えるので、勉強になれてないお子さんも抵抗なく勉強を始められます。
2.ライフスタイルに合わせた勉強

例えば塾や通信教材では、一ヶ月あたり進むべき分野が決められています。
そして決められた範囲をこなすために、毎週決められたタイミングで決められた時間勉強を進めることになります。
一方、タブレット教材の場合、もっと柔軟に時間を使うことができます。
学校に行く前の朝の10分、夕食を食べる前の10分など、一日の中でスキマ時間を使って勉強ができます。
また、気が進まない日には無理をしない、その分頑張れそうな日にはたくさん進めるなど、ペース配分を自分でコントロールすることができるのです。
例えば習い事をされているお子さんの場合、毎週まとまった時間を塾に通うために確保することは難しいのではないでしょうか。
そんなお子さんの場合も、スキマ時間を使って勉強を進められることがタブレット教材の魅力の一つです。
3.採点・復習に手間いらず

他の手段で自宅学習をする際、壁になるのは採点の手間と復習の手間です。
せっかく問題を解いてもきちんと丸付けせず解きっぱなしにしてしまう子もいます。
成績アップには自分の苦手を発見することが必要です。
そして苦手の発見には丸付けが必要です。
丸付けをおざなりにするためになかなか成績が上がらにくいケースもよくみられます。
そしてまた、丸付けをしても、間違ったところの復習をおざなりにしてしまう子もいます。
なぜなら、復習って面倒くさいのです。
自分がいつ何を解いて、どこを間違ったのか、膨大なプリントの山から探すのはそれだけで時間を食います。
ついつい復習が後手に回り、なかなか学んだことが定着しません。
タブレットを使えば、採点は自動で行われます。
解き終わった瞬間に、自分が躓いたところがわかります。
物によっては復習問題も適したタイミングで勝手に出題してくれます。
2.スマイルゼミの位置づけは?

ちゃれんじタッチ、Z会、RISU算数など、巷にタブレットはたくさんあります。
これらと比較してスマイルゼミはどのような位置づけなのでしょう。
学習速度と問題のレベルという2軸で評価すると、スマイルゼミは学校と同じ進度で教科書レベルの問題を解くことになります。
まずは学校の予習復習をやろう!というお子さんには適しているかもしれません。
一方で
- もっとときごたえがある問題にチャレンジをしたい!
- どんどん先に進んで新しいことを知りたい!
というお子さんには物足りないかもしれません。
ちなみにZ会は学校と同じ速度で頭を使う応用的な問題を解ける教材。
RISU算数は自分のペース(ほぼ皆先取り)で頭を使う応用的な問題を解ける教材です。
3.タブレット学習は続かないの?

さて、タブレット教材には様々な良い点が有りました。
しかし「ハマってくれたのは最初だけ」、「続かない」という声も聞こえてきます。
なぜこのような事態になるのでしょうか。
1.問題のレベルが合っていない
タブレット教材を使うと基本的には一人で問題をとき進めることになります。
すると問題が難しすぎたり易しすぎたりしても、周囲の大人が気づいてあげられないのです。
問題のレベルがちょうどいいことは大切です。
問題が難しすぎると解けなくて辛いですし、自分は勉強が出来ないのだと自身を失ってしまいます。
易しすぎると簡単すぎてつまらないなと感じてしまいやすいのです。
2.強制力が働かない
タブレット学習では、家で勉強を進めることになります。
テレビやゲーム、お友達からのお誘いなどお家にはたくさんの誘惑があるのです。
もし塾に通うのであれば、塾に到着すればそこは勉強のための空間です。
先生の目もありますし、否が応でも勉強をします。
ところが家には誘惑を断ち切るための強制力がないのです。
3.自分の成長が見えづらい
がんばった分だけ自分の成長を実感できるとやる気が湧いています。
ところがタブレット教材では、成長の実感が持てないまま延々と問題を解き続ける作業になってしまいがちです。
塾では実力テストなどを通じて自分の成績の伸びや周囲と比較した立ち位置を知ることができます。
基本的に一人で学習を進めるタブレット教材ではそのような機会は得られにくいのです。
4.継続してタブレット教材を使うためのコツ

1.適したタブレット教材を吟味する
一口にタブレット教材と言っても、問題のレベルや進度は様々です。
もしスマイルゼミを使っていて
・問題が易しすぎる
・進む速度がおそすぎる
ことでお子さんがつまらないと感じているようならZ会やRISU算数などに変えてみるのも一つの手です。
2.親御さんが声掛けをする
お勉強が嫌いでないと言えど、自分の力だけで他の誘惑に勝つのは難しいものです。
しかしお家で勉強する以上、そうも言っていられません。
なかなかテレビの前を離れられない、勉強にとりかかれない、というときには「勉強しようか」と声をかけてあげましょう。
3.外部のテストを利用しモチベーションUP
たとえば早稲田アカデミーや四谷大塚など、有名な塾では模試を外部にも公開しています。
定期的にそれらに参加し、自分の成績の伸びや、他の子と比べたときの立ち位置を実感する機会を作りましょう。
ちなみに模試の利用とまではいわなくとも、親御さんが褒めてあげるのも意外とよく効きます。
大事なのは自分はがんばれているのだと実感する機会を作ることです。
5.まとめ
数あるタブレット教材の中でもスマイルゼミは学校と同じペース、教科書レベルの問題という点に特長があります。
スマイルゼミを使って勉強することには様々なメリットはありますが、お家で続けるのが難しいのもまた事実です。
・適したレベルのタブレット教材を選んであげる
・親御さんが声がけする
・外部のテストや親御さんから褒めることでモチベーションを上げる
などが順調に学習を進める鍵です。
お子様の教材選びの参考になれば幸いです。
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら