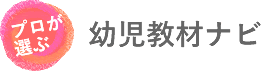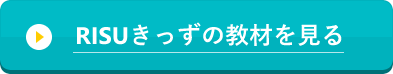幼児教育を扱った記事でよく話題に挙がる「七田式」。
子供向け学習を提供する会社のようですが、色々とよくない噂も目立ちます。
そこで今回は、七田式教育についてやめた、もしくは退会した方の理由、口コミを調べてみました。
1.そもそも「七田式」って?
「七田式教育」とは七田眞が提唱した独自の教育理論に基づく教育方法のことで、全国各地の教室で行われている講習やプリントの販売などを通して実践されています。
「天才を育てる」とも言われる七田式教育は、早期教育や英才教育に応用されています。
2.「七田式」のメリット
1.学習内容の充実
七田式の学習では、「もじ」「かず」「ちえ」の三つに分けて学習を進めていくことが出来ます。
「ちえ」
「ちえ」のプリント作業では、社会生活で必要な常識に関する学習やモノの名前、生活していく上で必要な基礎的な概念を学びます。
「外」「中」といった抽象的な思考力を身につけるための教材と言えますね。
「もじ」
文字と言うものに触れ、イラストと名前を一致させることによって、基本的な文字を自分で読めるようになるというレベルから出発します。
その後、動詞や反対語の使い分け、やがては文字を自分で書けるようになるレベルにまで到達することを目標とします。
「〇×」をつけるという形式の問題や、線を引く問題、色塗りを通して、日常生活の中で多く触れるモノに対する理解を深めることが出来ます。
「かず」
まずは声に出して数字を読むことからはじまります。
声に出して読むことによって、数字を子どもの頭に定着させ、数に慣れ親しんでもらうという効果があるようです。
そこから段階的に難易度が上がり、イラストを通じて数字を選択させる問題が出題されることもあります。
順列や比較や数量、空間把握など、バリエーション豊富な多くの問題に取り組むことができます。
2.自宅での学習習慣を育てる
くもんを始めとする学習教室形式の場合、最大の悩みのひとつとなるが、送り迎えです。
たとえば英語教室やピアノ、プールなどの習い事がある場合、重ねて送り迎えが必要になる場合、保護者の負担がかなり増えることになってしまいます。
また送り迎えの機会が増えることはお子様にとってもストレスとなり、決して良い影響を与えません。
また送り迎えがないのも家庭学習の良い点ですが、家庭で学習する習慣がつくという点も大きいです。
家庭学習の習慣をつけるということは、のちに小学校、中学校と進むにつれて必要な「勉強」という習慣を早いうちから生活の一部として取り入れることができます。
しかし家庭学習の定着という面だけで見た場合、公文式やここ数年で台頭したタブレット教材、教育アプリといった家庭用学習教材の数々と比べると、有効であると言えるでしょうか?
主に理数面での学習効果や子どもの取り組みやすさ、モチベーションの維持という点においてそこまで優れているとは言えないのではないか、と疑問視する声もあります。
3.親子のコミュニケーションをとることができる
七田式のプリントを子どもと一緒に解くことで、親子のコミュニケーションをとることができます。
子どもをひざの上に抱き寄せて、親子の触れ合いツールとして七田式のプリントを活用することもできます。
しかしこれも、他の教材と比べたときに特徴的と言えるほどのものではありません。
親子の触れ合いを目的とするならば、七田式を使わずとも普段からコミュニケーションを心がけていればそれで済む話なのでは?という疑問が沸いてきます。
3.「七田式」をやめた理由
ネット上の評判をもとに、七田式をやめた理由をいくつかピックアップしてみました。
七田式の評判が良くない理由には、そもそも早期教育の弊害や問題点が多く指摘されており、七田式に関係なく早期教育、幼児教育全般に対する批判が背景にあるとも言えます。
例として、よく指摘されることの多い批判点を挙げてみますと、
- 「詰め込み式」の教育を長く続けていると、子どもの脳がパンクしてしまう。「不登校になる」「激しく反抗するようになる」「学力が伸びなくなる」「食欲不振、神経的な不調が慢性化する」といった問題が起こることも。
- マニュアル的な教育を施されることで、主体性を欠いた「指示待ち人間」になってしまう恐れがある。幼児期の一方的で視野狭窄な教育は、子どもの創造性を奪い、自由な発想を産み出す力を萎縮させてしまう。
- 「保護者の要望に応える」ことに特化した結果、自己肯定感の極端に低い子に育ってしまうこともある。
そうした点の他に、七田式退会者が「やめた原因」として挙げるもののいくつかを紹介します。
1.科学的根拠に疑問
独特の教育方法を提唱し実績を出しているかのように見える七田式ですが、実はその教育法に科学的な根拠はありません。
イラストを多用した七田式の教育は、確かに暗記力は伸びているかのように思えますが、それが受講者の東大合格といった実績に直接結びついているかどうかはわかりません。
また、七田式の教育で実績を上げている方の多くは通信教育ではなく教室で講義を受けているのではないかという指摘もあり、通信教育としての七田式にどこまで効果が証明されているのかは疑問です。
「七田式」で検索すると、「七田式」の教育方針や創始者の言動を「宗教」「オカルト」「ニューエイジ」「疑似科学」とする指摘も多く見ることが出来ます。
これは、「七田式」が「右脳の発育」を重視する立場をとること、また精神論的な言動が散見されることが原因のようです。
2.問題が単調
七田式の問題は、先述したとおり「ちえ」「もじ」「ちず」の三つに分かれています。
しかしそれらはいずれも単純な作業の繰り返しであり、やっていくうちにだんだん飽きてきてしまいます。
こうした作業的な学習の積み重ねは、非効率的であるばかりか、子どもに勉強に対する苦手意識を植え付ける結果になってしまいかねません。
延々と続く単純作業はわれわれ大人から見ても決して楽とは言えないものですが、お子様からしてみれば殆ど苦痛と言ってもいいほどのストレスにもなります。
お子様のモチベーション維持、学習習慣の定着という面から見ても、「作業感」のあるプリント教育はあまり適切であるとは言えません。
七田式のプリントは、イラストが豊富でわかりやすくはありますが、問題の質が高いということを必ずしも意味するものではないようです。
3.料金が高い
七田式の料金は、教材を30冊まとめて購入しなければならないため高めに見積もらなければいけません。
教材費13,885円と年会費4,104円が二重でかかってしまうという難点があります。
30冊まとめて購入しなければいけないため、もしお子様が途中でリタイアした場合には痛手になりますね。
慎重に考えざるをえない原因になっているのではと思います。
4.まとめ
七田式のプリント教材について、メリット、デメリットや退会者の声を紹介しました。
独特の教育方法でそれなりの実績もあり、利用者の中から東大をはじめとした難関大学に合格する方もいます。
一方で、科学的に効果の証明されていないオカルトチックな側面があったり、プリントが学力向上にどの程度寄与するのかが不透明であったり、疑問点が多い教材でもあります。
プリントのお値段も安くはないので、一長一短といったところでしょうか。
▼ 読んでおきたい関連記事はこちら